会員登録時に「登録確認のメール」が届きます。
携帯・スマホなどでお申し込みの場合、info@ginken.jpのメールが受け取れる設定をお願いします。
銀行実務2025年11月号
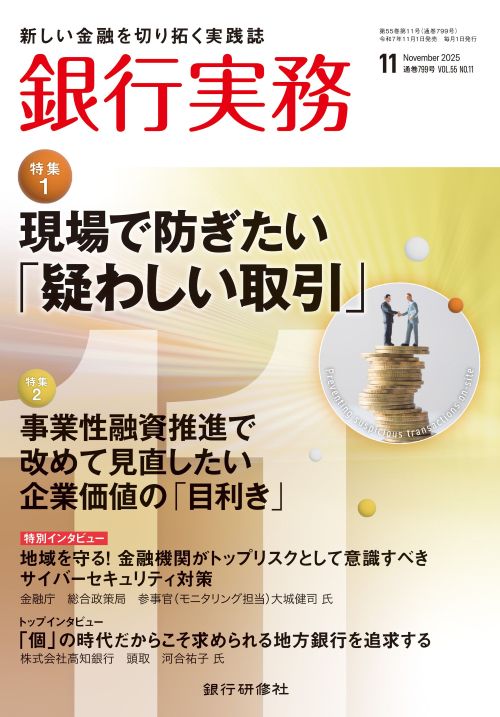
特別インタビュー 地域を守る!金融機関がトップリスクとして意識すべきサイバーセキュリティ対策
近時、サイバー攻撃が高度化・多発化しており、地域金融機関においては最もリスク管理を行うべき対策の一つに挙げられる。今回、金融庁 総合政策局 大城健司参事官(モニタリング担当)に、中小・地域金融機関がサイバーセキュリティにおいてとるべき対応、特に現場の行職員一人ひとりが行うべき「サイバーハイジーン」について触れ、ご解説をいただいた。
金融庁 総合政策局 参事官(モニタリング担当) 大城 健司 氏
トップインタビュー 「個」の時代だからこそ求められる地方銀行を追求する
高知銀行 河合祐子頭取は、人口減少下においても地域金融の可能性を強く見据える。「個」が重視されるようになった今だからこそ、デジタル化が進展してもなお、face to face な関係構築に優位性がある地域金融機関に強みがあるというのが同氏の主張だ。
株式会社高知銀行 頭取 河合 祐子 氏
特集1 現場で防ぎたい「疑わしい取引」
警視庁が公表した「犯罪収益移転防止に関する年次報告書」によれば、令和6 年における「疑わしい取引」の届出件数は80 万件を超え、過去最多を記録した。実体のない又は実態の不透明な法人が悪用された事例のほか、犯罪組織が支配する法人口座が、犯罪収益の隠匿先や犯罪収益を経由させる「トンネル口座」として悪用されている事例も指摘されているようだ。FATF 第 5 次対日相互審査を控え、特に、現場で対応にあたる行職員においては、疑わしい取引に関する実務知識を再確認し、適切な対応を行うことが不可欠である。本企画では、「疑わしい取引」について、参考事例の解説、また実質的支配者の確認や継続的顧客的管理といった必要な対応について解説した。
Part1 参考事例と関連注意事項/届出態勢構築と要否判断の要点
岩田合同法律事務所 弁護士 深沢 篤嗣
Part2 実質的支配者の確認と継続的顧客管理の実務
潮見坂綜合法律事務所 弁護士 鈴木 正人
GMOあおぞらネット銀行 弁護士 山﨑 太郎





B5判・84頁
特集1 現場で防ぎたい「疑わしい取引」
定期購読のお申込はこちら